
パーパス・ドリブンな人と組織をつくるには~ 越境学習を活用したハウス食品のリーダー育成に学ぶ〜
ポストコロナ時代のキーワードとして「パーパス」を耳にすることが多くなってきました。一方でその重要性を理解しつつ、パーパスドリブンな組織経営やリーダー育成方法について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は越境学習を通じた人材育成に取り組むハウス食品グループ本社より、管理本部長・大澤氏と、越境学習の経験者である加藤氏と中西氏をお迎え。同社の事例から、パーパスドリブンな人と組織づくりについて学んでいきます。(本レポートは2022年6月29日に実施したセミナーを元に作成しています)
コロナ禍で求められる「パーパスドリブンなリーダー」とは
最初にクロスフィールズ小沼より、パーパスを持ったリーダー育成の重要性や、越境学習の効果を説明しました。
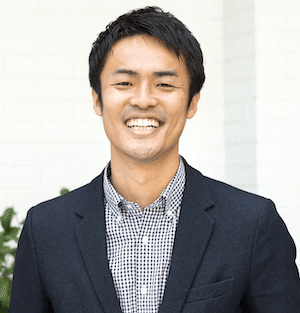
青年海外協力隊、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て2011年クロスフィールズ創業
小沼:先行きの見えないVUCAの時代と言われるなか、「パーパス」の重要性が語られる機会が増えているのではないでしょうか。パーパスの定義は様々ありますが、個人的には「自らが生涯を通じて体現したい志」だと考えています。揺るぎない自分の志を持ち、それを価値判断の基準として答えが見えない状況でも決断できる。そんなリーダーが、ますます組織や社会に必要とされていると感じます。
パーパスを中心に据えて仕事をすることで、自分・仕事・社会の3つの関係がつながっていきます。自分自身や自分の仕事が社会に与える影響を自覚し、中長期的な社会的インパクトを実感しながら目の前の業務を進めていくリーダーはモチベーションの高いチームを創れるし、高い成果を生み出せるのです。
では、そんなリーダーを育成するにはどうすればいいのか。マクロミル社と当団体が2019年に実施した大規模リサーチでは、パーパスを育むには「越境学習」が効果的だと分かってきました。以下では越境学習の1つである留職プログラムを例に説明していきますが、リサーチの結果、総じて一般社員よりも留職経験者は「所属組織や仕事への満足度」が高いとわかっています。


留職プログラムとは日本のビジネスパーソンが国内外の社会課題の現場へ飛び込み、一定期間にわたり現地の課題解決に取り組むものです。留職参加者は越境の経験を通じて「自身が仕事を通じて実現したいこと」を見つめ直していきます。個人のパーパスと所属組織のパーパスが繋がることを経験するため、越境後に所属元の企業に戻ってからも会社のパーパスと自身とのつながりが強まる傾向だと考えられます。
個人のパーパスが組織ダイバーシティにつながる
小沼:ここまで留職を通じたリーダー育成の特徴をお伝えしましたが、ここからは実際に留職を活用して人材育成に取り組むハウス食品グループ本社・管理本部長の大澤さんより、同社における留職の位置付けや導入目的について語っていただきます。

大澤:当社では留職プログラムを「ダイバーシティの実現」の目的で2015年から導入、今年で8期目になります。多様な経験をし、自分らしい働き方やリーダーシップを一人ひとりの社員に実現してもらいたいと考えているのです。
この背景にはグループ理念とステークホルダーへの責任の考えがあります。当グループは「食を通じて人とつながり笑顔ある暮らしを共に作るグットパートナーをめざします」を理念としており、この「人」とは ①お客様 ②社員とその家族 ③社会 の3つのステークホルダーを表しています。
2018年からは中期経営計画においても「社員とその家族に対する責任」としてダイバーシティの実現を掲げ、組織と社員の成長を同期する試みを行っています。
ダイバーシティを推進するには「属性・経験・適性」という3つの視点で捉えることが重要だと考えています。「属性」は国籍や年齢、性別などが多様であることを指します。「経験」は、従来の業務から飛び出して様々なチャレンジをした人材が集まっていること。そして「適性」は自身の適性や個性を活かし、チームへ貢献することを意味しており、これは多様なリーダーシップのあり方を実現するものです。留職プログラムは経験と適性のダイバーシティを養う人事戦略に位置づけています。
小沼:今ではダイバーシティ戦略の一環として留職を位置付けていらっしゃいますが、導入当初は異なる目的だったと伺っています。いかがでしたか?

大澤:当時は「既存の枠組みを超えて新しい挑戦をしないと、長期的に企業が立ち行かない」という危機感がありました。そこで「社会課題の現場に越境し、普段の業務とはかけ離れた課題解決に取り組む」留職の導入を決意したのです。全く新しい人事施策でしたが、まずは周りを巻き込んで進め、人材育成として効果があることを証明していきました。
8年にわたって留職を実施する中で、このプログラムの最大の効果は「参加者が自身のあり方やパーパスを深めることで、自らのリーダーシップを見つけ、それらを周囲に伝播するようになること」だとわかってきました。
上が決めたリーダーシップの形を押し付けるのではなく、彼ら・彼女らが自分らしいリーダーシップを言語化し、発露していく。これは「リーダーシップ講座」のような座学では提供できない大きな価値です。
一方で留職が参加社員に与える効果を組織全体に伝搬し、組織変革にしていくには時間がかかります。それでも越境学習や留職がもたらす価値を信じ、中期経営計画の施策に位置づけたことは、組織変革に繋がりうる一歩だと感じています。
経験者が語る「留職を通じた学び」
小沼:ここからは留職に参加した加藤さんと中西さんより参加のきっかけや経験について伺っていきます。加藤さんは2015年にインドネシア、中西さんは2021年に日本で留職を経験しています。

加藤:私は2015年、入社4年目のときにインドネシアのカカオ農家を支援するソーシャルベンチャーに留職しました。現地ではチョコレート製品の販売からパッケージデザイン等、幅広い業務を経験しました。
留職に参加したきっかけは、「日本のマーケットでの経験だけでは、グローバルで勝負できない」という危機感でした。海外で事業を広めていくにはどうすればいいか考えていたとき、ちょうど留職の社内公募を見つけ、応募しました。

中西:私は入社以来、ずっと研究所で勤務していたため「一度外に出て、自分の仕事と社会のつながりを見つめ直したい」という思いから7年目の2021年に留職へ参加しました。派遣先のマザーハウスでは、「食」をテーマにした事業を行うチームでチョコレート製品の製造から店頭販売まで担当しました。
小沼:お二人は派遣時期も場所も異なりますが、留職ではどのような学びがありましたか?
加藤:シンプルですが「相手との信頼関係があってこそ、仕事を創っていける」ということです。留職中に起こったある出来事で、これを実感しました。
インドネシアで活動していたある日、製品の在庫データと実際の数がズレていることを発見しました。最初は担当者に在庫を数えるようお願いしたのですが、なかなか依頼を聞いてくれなかったんです。そこで「一緒に数えよう」と提案したらようやく在庫の計算をしてくれて、次第に私がいなくても担当者が在庫管理をするようになりました。
言語や文化が異なる相手でも、信頼関係は築ける。このとき、そう実感したんです。この経験は現在のベトナム赴任でも活きていて、部長職となった今でも営業の現場やイベントでの販促に同行しています。ベトナム語はわからなくてもボディランゲージなどで相手とコミュニケーションを取り、信頼関係を築く意識をしています。

中西:私は留職で「食に関する事業を通じて環境問題に取り組みたい」という志を見つけることができたのが大きいです。その背景には、マザーハウスで働く方々からの刺激がありました。彼らは「自分はこんなことをしたくて、この組織で働いている」という、強い意思を持っていました。
そんな方々と働いていると、私も「自分は何のために今の会社で働いているのか」と考えるようになったんです。これをクロスフィールズの担当プロジェクトマネージャーが1on1で深堀りしてくれて、最終的に「事業を通じて、自分の関心事である環境問題に取り組みたい」という志を見つけることができました。

海外と国内に違いなし!大切なのは一人ひとりの経験を組織知にすること
小沼:コロナ禍において、留職プログラムは新興国だけではなく国内でも2020年から派遣を開始しています。大澤さんに伺いたいのですが、国内外どちらのプログラムも導入しているなかで感じる違いはありますか?
大澤:派遣先が海外・国内で、成果に違いが出るとは思っていません。一人ひとり異なる経験をして新たな視点を持ち帰ってきているからです。
海外派遣は「言語や文化の壁を乗り越える」という、日本ではできない修羅場体験を通じて大きく成長することができます。一方で国内派遣は言語の壁がない分、派遣先が取り組む課題や事業にさらに深く潜り込み、その過程で自分自身の志を見つけていく経験をしているように思います。そのため、今後も一人ひとりの参加者の特性や彼らの意思を組み合わせて、舞台を設定していきたいと考えています。
小沼:越境して自身のダイバーシティを広げたメンバーを、組織としてどう受け入れているのでしょうか。
大澤:留職後の配属は本人の経験と意志をできる限り尊重し、たとえば中西さんは研究職に戻るのではなく新規事業に、加藤さんは海外事業を任せる、などしています。
これまでの施策を通じて、一人ひとりの経験やリーダーシップのダイバーシティは広がったと感じています。次のステップとして「現場が彼らをどうインクルージョン(包摂)していくか」に、組織として取り組んでいます。

中西:たしかに留職中と現在では仕事の進め方が大きく異なっています。組織の規模や事業内容が違うから当たり前かもしれません。そんな環境でも留職先のマザーハウスで体感した「動きながら考える」というスピード感を意識し、仕事に取り組むようにしています。
小沼:ありがとうございます。最後に大澤さんより、人事施策に悩んでいる方々へメッセージをいただけますか?
大澤:何かを変えるためには、一歩を踏み出さなければ始まりません。これは組織も個人も同じです。新しい挑戦に迷っているなら、ぜひ踏み出してほしいです。その一歩が組織の変化につながると信じています。
**
今回登壇した中西さんの留職活動は、以下のレポートからご覧いただけます。
加藤さんも参加した留職プログラム(新興国派遣)の様子は以下の動画をご覧ください。

